チャイナショック (国際経済学)
 | この項目では、国際経済学におけるチャイナショックについて説明しています。広義のチャイナショックについては「チャイナショック」を、2015年の中国株価の値下げについては「中国株の大暴落 (2015年)」をご覧ください。 |
| 経済学 |
|---|
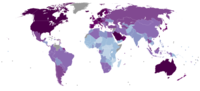 地域別の経済 |
| 理論 |
| ミクロ経済学 マクロ経済学 数理経済学 |
| 実証 |
| 計量経済学 実験経済学 経済史 |
| 応用 |
| 公共 医療 環境 天然資源 農業 開発 国際 都市 空間 地域 地理 労働 教育 人口 人事 産業 法 文化 金融 行動 |
| 一覧 |
| 経済学者 学術雑誌 重要書籍 カテゴリ 索引 概要 |
| 経済 |
|
|
|
チャイナショック (英: The China shock) は、国際経済学の文脈では、2001年の中国の世界貿易機関への加盟前後に中国から米国や欧州への輸出が増加したことと、それによる輸入国における経済的な影響のこと[1][2]。
概要
中国からの輸入の急増によって、米国の製造業の雇用者数が55万人減少したことが示されており、これは2000年から2007年までの米国の雇用者数の減少(180万-200万人)の16%に相当する[3]。また別の研究はチャイナショックによる雇用の減少は180万から200万人であるとしている[4]。200万から240万人とする研究もある[5]。製造業の雇用減少はノルウェイやスペイン、ドイツでも観察されている[6][7][8]。米国において中国との輸入競争に直面した地域では、失業率が上昇、労働市場参加率が低下、さらに賃金が低下したことが示されている[9]。
製造業など米国の特定の市場では負の影響を受けたが、貿易全体(輸出入)を考慮すると1991年から2011年の期間で米国経済全体として雇用と厚生が上昇したことも示されている[4][3]。これらの主張はデービッド・オウター(英語版)やデービッド・ドーン(英語版)、ゴードン・ハンソンらに反駁されており、彼らは「国全体で見ると、輸入競争に直面した産業では雇用が減少しており、他の産業の雇用増加は輸入競争産業の雇用減少を相殺するほど大きくない」と述べている[10]。2017年に発表された研究では、輸出入を考慮するとドイツ経済では雇用の増加の効果があったとされている[11]。
消費財の輸入を通じたチャイナショックは2006年頃に終焉しているが、資本財の輸入を通じた影響は2012年頃まで継続し、現在も特定の品目の輸入を通じた影響があることが示唆されている[1]。また、チャイナショックの米国経済への影響を研究してきているデービッド・オーター、デービッド・ドーン、ゴードン・ハンソンは環太平洋パートナーシップ協定を支持している[12]。彼らは、TPPの締結によって米国が比較優位のある知識集約的な産業での貿易が増加し、中国がその加盟国になれば中国に法令遵守・品目規格の遵守についての圧力をかけることができ、TPPを反故にしても製造業の生産を米国に戻すのにあまり貢献しないと述べている[12]。
背景
1991年時点は米国では中国からの輸入はGDPで1%たらずであった[13]。しかし、1990年代のコミュニケーション技術・輸送技術の改善によって生産拠点を中国などの低賃金国に移転することが容易になった[14]。2001年の中国のWTOへの加盟、中国の市場経済化、政府の市場への介入の減少によって中国の輸出企業の生産性が改善した[15]。中国は1980年代から欧州と米国から最恵国待遇を受けていたが、最恵国待遇の地位は毎年米国議会で承認されなければならなかったため、中国の輸出企業が直面する関税率は毎年更新の可能性があった[15]。これによって、中国からの輸出は低水準にとどまっていた[15]。
政治的影響
中国からの輸入の急増によって、ポピュリズムとグローバリゼーションへの懐疑論が高まったことが示されている[16]。また、イギリスの中国との輸入競争に直面した地域ではイギリスの欧州連合離脱への国民投票で賛成を投じた人が多かったことも示されている[17][18][19]。
また、中国からの輸入の急増によって米国内で政治的二極化が強まったことも示されている[20]。さらに、中国からの輸入が2016年アメリカ合衆国大統領選挙におけるドナルド・トランプの勝利に影響したことも示唆されている[21]。それによると、もし米国における中国からの輸入が実際よりも50%少なければ、ミシガン州、ウィスコンシン州、ペンシルバニア州では民主党候補が勝利していたことが示唆されている[21]。
イタリアでは、中国との輸入競争で打撃を受けた繊維に特化していた地域で同盟への支持が拡大したことが示されている[22]。
社会的影響
中国からの輸入の急増によって、米国で高校卒業率が上昇したことが示されている[23]。輸入競争によって高校を卒業していない労働者の就業状況が悪化したからであると考えられている。経済学者サミュエル・ハモンドは、2000年の10月に中国に恒久的通常貿易関係(英語版)(PNTR)が与えられることが決定し、2001年に中国がWTOに加盟したことによって様々な社会的な影響があったと述べている[24]。彼は、「PNTRは今世紀の米国の様々な負の側面と関連している。負の側面とは、何百万もの高給な製造業の職が失われたこと、婚姻率の低下、自殺の増加、住宅価格の上昇、都市部の中世レベルの高い所得格差、政治的二極化、左右のポピュリスト政治の席巻、民主政治への信頼の失墜などである。これらすべてを貿易のせいにするのはもちろん早計であるが、チャイナショックはこれらすべてと一次的効果、あるいは政治を通じた影響などの二次的効果を通じて関連しているように思える。」と述べている[24]。
また、米国において、中国からの輸入の急増で雇用が失われたことで、軍隊への入隊が増加したことも示されている[25][26]。
出典
- ^ a b Brad W. Setser. “When Did the China Shock End?” (英語). Council on Foreign Relations. 2021年12月4日閲覧。
- ^ Lipton, Gabe (2018年8月14日). “The Elusive 'Better Deal' With China” (英語). The Atlantic. 2019年6月10日閲覧。
- ^ a b Caliendo, Lorenzo; Dvorkin, Maximiliano; Parro, Fernando (2019). “Trade and Labor Market Dynamics: General Equilibrium Analysis of the China Trade Shock” (英語). Econometrica 87 (3): 741–835. doi:10.3982/ECTA13758. ISSN 1468-0262.
- ^ a b Feenstra, Robert C.; Sasahara, Akira (2018). “The 'China shock,' exports and U.S. employment: A global input–output analysis” (英語). Review of International Economics 26 (5): 1053–1083. doi:10.1111/roie.12370. ISSN 1467-9396. http://www.nber.org/papers/w24022.pdf.
- ^ Acemoglu, Daron; Autor, David; Dorn, David; Hanson, Gordon H.; Price, Brendan (2015-12-21). “Import Competition and the Great US Employment Sag of the 2000s”. Journal of Labor Economics 34 (S1): S141–S198. doi:10.1086/682384. hdl:1721.1/106156. ISSN 0734-306X. https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/123736/1/Import%20competition_Acemoglu_ver%C3%B6ff.pdf.
- ^ Balsvik, Ragnhild; Jensen, Sissel; Salvanes, Kjell G. (2015-07-01). “Made in China, sold in Norway: Local labor market effects of an import shock”. Journal of Public Economics. The Nordic Model 127: 137–144. doi:10.1016/j.jpubeco.2014.08.006. hdl:11250/196942. ISSN 0047-2727. https://econpapers.repec.org/RePEc:iza:izadps:dp8324.
- ^ Donoso, Vicente; Martín, Víctor; Minondo, Asier (2015-01-01). “Does Competition from China Raise the Probability of Becoming Unemployed? An Analysis Using Spanish Workers' Micro-Data” (英語). Social Indicators Research 120 (2): 373–394. doi:10.1007/s11205-014-0597-7. ISSN 1573-0921.
- ^ Dauth, Wolfgang; Findeisen, Sebastian; Suedekum, Jens (2014). “The Rise of the East and the Far East: German Labor Markets and Trade Integration” (英語). Journal of the European Economic Association 12 (6): 1643–1675. doi:10.1111/jeea.12092. hdl:10419/88626. ISSN 1542-4774.
- ^ Hanson, Gordon H.; Dorn, David; Autor, David H. (2013). “The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States” (英語). American Economic Review 103 (6): 2121–2168. doi:10.1257/aer.103.6.2121. ISSN 0002-8282.
- ^ https://economics.mit.edu/files/12751
- ^ Suedekum, Jens; Findeisen, Sebastian; Dauth, Wolfgang (2017). “Trade and Manufacturing Jobs in Germany” (英語). American Economic Review 107 (5): 337–42. doi:10.1257/aer.p20171025. hdl:10419/149134. ISSN 0002-8282. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/149134/1/877243093.pdf.
- ^ a b Autor, David; Dorn, David; Hanson, Gordon H.. “Why Obama's key trade deal with Asia would actually be good for American workers”. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/03/12/why-obamas-key-trade-deal-with-asia-would-actually-be-good-for-american-workers/ 2016年5月24日閲覧。
- ^ “Reconsidering the 'China shock' in trade”. VoxEU.org (2018年1月18日). 2019年6月10日閲覧。
- ^ Irwin, Neil (2018年3月23日). “Globalization's Backlash Is Here, at Just the Wrong Time” (英語). The New York Times. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/2018/03/23/upshot/globalization-pain-and-promise-for-rich-nations.html 2019年6月10日閲覧。
- ^ a b c Autor, David H.; Dorn, David; Hanson, Gordon H. (2016-10-31). “The China Shock: Learning from Labor-Market Adjustment to Large Changes in Trade” (英語). Annual Review of Economics 8 (1): 205–240. doi:10.1146/annurev-economics-080315-015041. ISSN 1941-1383. http://www.nber.org/papers/w21906.pdf.
- ^ Broz, J. Lawrence; Frieden, Jeffry; Weymouth, Stephen (2021). “Populism in Place: The Economic Geography of the Globalization Backlash” (英語). International Organization 75 (2): 464–494. doi:10.1017/S0020818320000314. ISSN 0020-8183.
- ^ Stanig, Piero; Colantone, Italo (2018). “Global Competition and Brexit” (英語). American Political Science Review 112 (2): 201–218. doi:10.1017/S0003055417000685. ISSN 0003-0554.
- ^ Ballard-Rosa, Cameron; Malik, Mashail A.; Rickard, Stephanie J.; Scheve, Kenneth (2021). “The Economic Origins of Authoritarian Values: Evidence From Local Trade Shocks in the United Kingdom” (英語). Comparative Political Studies. doi:10.1177/00104140211024296. ISSN 0010-4140. https://doi.org/10.1177/00104140211024296.
- ^ Steiner, Nils D.; Harms, Philipp (2021). “Trade shocks and the nationalist backlash in political attitudes: panel data evidence from Great Britain”. Journal of European Public Policy. doi:10.1080/13501763.2021.2002925. ISSN 1350-1763. https://doi.org/10.1080/13501763.2021.2002925.
- ^ Majlesi, Kaveh; Hanson, Gordon H.; Dorn, David; Autor, David H. (2016-09-01). “Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure” (英語). CEPR Discussion Paper No. DP11511 (Rochester, NY). SSRN 2840708.
- ^ a b “A Note on the Effect of Rising Trade Exposure on the 2016 Presidential Election”. 2021年12月4日閲覧。
- ^ Peter S. Goodman and Emma Bubola (2019年12月5日). “The Chinese Roots of Italy's Far-Right Rage”. New York Times. https://www.nytimes.com/2019/12/05/business/italy-china-far-right.html
- ^ Greenland, Andrew; Lopresti, John (2016-05-01). “Import exposure and human capital adjustment: Evidence from the U.S.”. Journal of International Economics 100: 50–60. doi:10.1016/j.jinteco.2016.02.002. ISSN 0022-1996.
- ^ a b “The China Shock Doctrine”. 2021年12月4日閲覧。
- ^ Dean, Adam (2018-12-01). “NAFTA's Army: Free Trade and US Military Enlistment” (英語). International Studies Quarterly 62 (4): 845–856. doi:10.1093/isq/sqy032. ISSN 0020-8833.
- ^ Dean, Adam; Obert, Jonathan (2019-10-18). “Shocked into Service: Free Trade and the American South's Military Burden”. International Interactions 46: 51–81. doi:10.1080/03050629.2019.1674298. ISSN 0305-0629.
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本概念 |
| ||||||||||||
| 理論・議論 | |||||||||||||
| モデル |
| ||||||||||||
| 分析ツール |
| ||||||||||||
| 結果 |
| ||||||||||||
| 貿易政策 |
| ||||||||||||
| トピック |
| ||||||||||||
| 近接分野 | |||||||||||||
| Category:国際経済学 Category:貿易 Category:国際経済学者 | |||||||||||||










